『 山 』
城南センターに勤務しておりますT.Tです。
当センターに赴任いたしまして早4年が過ぎました。
そんな中で毎日楽しみにしている事があります。
それは、「山」です。
この山は、当センターの方角から見ると誠に立派な形をしておりまして
(この方角からしか、この形に見えないのです・・・・)
晴天によく映え、周りの風景とも相まって四季折々の美しさを感じさせてくれています。
当センターでは、主に量販向けのペットフードを出荷しておりますが、発足当初に比べると年々の取扱量も増えてきまして、曜日によっては1日で大型車輛で27台以上、パレットで約500パレットを出荷しており、皆の協力と努力を少しずつ少しずつ積み重ねて4年間を過ごしてきました。
旧城南センターが熊本地震で消失してから、旧センターの従業員の仕事の継続確保のために引っ越してきて、何とか今のところまでやってきました。
毎日バタバタとしている中で、ちょっとだけ「ホッとする」時間をこの山にもらってきた次第であります。
地元の従業員に山の名前を訊いたら、「甲佐岳」という名前だそうです。
いつかこの山に昇って、山頂から当センターを眺めてみたいと思っています。
 遠くに望む「甲佐岳」
遠くに望む「甲佐岳」
 出荷準備中の倉庫内
出荷準備中の倉庫内
 配送を待つ商品
配送を待つ商品
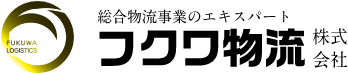



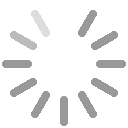
 ペット用品の出荷
ペット用品の出荷 LEDに換装された天井
LEDに換装された天井 ペット用品の入荷・格納
ペット用品の入荷・格納 商品の集荷(ピッキング)作業
商品の集荷(ピッキング)作業 配送先への出荷準備
配送先への出荷準備 ペット用品の入荷・格納
ペット用品の入荷・格納 スーパー様への出荷検品
スーパー様への出荷検品 猫用トイレの出荷準備
猫用トイレの出荷準備 業務用ビールの出荷
業務用ビールの出荷 スーパー様等への出荷
スーパー様等への出荷 出荷商品のピッキング作業
出荷商品のピッキング作業 集められた商品を検品中
集められた商品を検品中
 お問合せフォーム
お問合せフォーム 求人応募フォーム
求人応募フォーム